メタディスクリプション: 本記事では、ガソリン1リットル当たり53.8円を占める「暫定税率」の内訳や二重課税の問題点、トリガー条項が発動しない理由、2026年4月に有力視される廃止時期の行方、家計・物流・地方経済への影響、そして代替財源の議論までをわかりやすく解説します。
ガソリン暫定税率とは
ガソリンに課される税金のうち、1974年のオイルショックを受けて「一時的な措置」として導入された上乗せ分(25.1円/L)を指します。目的は道路整備などの財源確保でしたが、40年以上経った現在も存続し続けています。
導入の背景と経緯
1970年代の急激な原油価格高騰により、政府は道路整備やエネルギー安全保障の財源確保を急務としました。そこで暫定的にガソリン税へ上乗せ課税を行い、期限ごとに延長してきたのが暫定税率です。2008年には失効・復活をめぐる混乱(いわゆる「ガソリン値下げ隊」騒動)も経験しましたが、結果的に制度は維持されています。
税額の内訳と二重課税問題
2025年6月現在、リットル当たりの税負担は以下の通りです。 区分税率(円/L) 本則税率(国税+地方税)24.3 + 4.4 = 28.7 暫定税率(上乗せ分)25.1 合計53.8
さらに消費税10%は、上記税金を含むガソリン本体価格に対して課税されるため、いわゆる「税に税をかける」二重課税構造となっています。この点は長年にわたり批判の的となっています。
トリガー条項が発動しない理由
2008年創設のトリガー条項は「レギュラーガソリンの全国平均価格が3か月連続で160円/L超」となった場合、暫定税率25.1円/Lを一時停止し価格を抑える制度です。しかし、2011年3月の東日本大震災後に財源確保を優先し凍結。現在も法改正がない限り発動不可の状態が続いています。
暫定税率廃止がもたらす影響
1. 家計(一般消費者)
- ガソリン価格が理論上約25円/L下落
- 普通車を年間1,000 L給油する世帯なら年間約25,000円の節約
2. 物流・物価
- 運送業・農業・漁業など燃料費の比率が高い業種はコスト減
- 輸送費の下落により、食品や日用品の価格も抑制効果が期待
3. 地方経済・観光
- 車移動のハードルが下がり、観光需要が回復・拡大
- 地域間物流コストも低減し、地方企業の競争力向上
4. 財政・インフラ
- 税収 約1.5兆円/年 が減少し、道路整備・公共交通の財源不足が懸念
- 高速道路の維持更新費や防災関連投資への影響が避けられない
現在実施されている価格抑制策
政府は2025年5月22日から段階的な補助金を再延長し、石油元売りに対し最大35円/Lを支給。小売価格ベースでは10円/Lの「見かけ値引き」を行っています。ただし、財政負担が大きく恒久策にはなり得ません。
今後の見通しと代替財源
与野党の合意では2026年4月を目途に暫定税率廃止を本格検討するとされています。代替財源の候補例は次の通りです。
- 走行距離課税(走った分だけ負担)
- 環境税の増額(炭素に連動)
- 道路特定財源の一般財源化
- EV充電課金の強化(ガソリン車と公平に負担)
ただし、いずれも導入には制度設計と国民理解が不可欠です。
まとめ
ガソリン暫定税率は本来「一時的」でしたが、50年近く延々と延長されてきました。
25.1円/Lの負担は家計・産業界に重くのしかかる一方で、年間1.5兆円もの税収を支える重要財源でもあります。
2026年4月の廃止が視野に入るなか、代替財源の確保が最大の課題となっており、国会審議の動向を注視する必要があります。

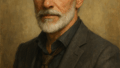

コメント