明治時代に制定された「教育勅語(きょういくちょくご)」は、日本の教育の基本的な考え方を示した重要な文書です。近代日本の道徳教育の中心にあり、戦前の学校では暗唱させられていました。この記事では、その内容と意味をわかりやすく解説します。
教育勅語とは何か?
教育勅語は、1890年(明治23年)に明治天皇が出した勅語(ちょくご)で、正式名称は「教育ニ関スル勅語」です。文部省(現在の文部科学省)が全国の学校に配布し、額に入れて掲げたり、朝礼で朗読されたりしました。
当時の日本は、西洋の文明を取り入れながらも「日本らしい道徳心」や「忠誠心」を大切にする教育を求めていました。そのため、教育勅語は、国民としての理想の生き方を説くものでした。
教育勅語の内容を簡単に説明
教育勅語は古い言葉で書かれていますが、主な内容は次のようにまとめることができます。
- 親を大切にし、兄弟仲良くする
- 夫婦は仲むつまじく、友だちは信じ合う
- 謙虚であり、他人に思いやりを持つ
- 勉強や仕事に励み、知識と才能を伸ばす
- 公益のために尽くし、社会の役に立つ
- 法律を守り、正しい道を歩む
- 国のために心を尽くし、天皇に忠誠を誓う
つまり、「家庭や社会の中での道徳」と「国家への忠誠」を両立させる生き方を説いているのです。
教育勅語の現代的な評価
戦後、日本国憲法と教育基本法が制定され、教育勅語は1948年に廃止されました。理由は、天皇への忠誠を強調しすぎて、戦時中の国家主義教育の中心となったためです。
しかし一方で、教育勅語の中には「親孝行」や「友情」「努力」「公共心」など、現代でも大切にされている価値観も含まれています。そのため、完全に否定するのではなく、道徳的な部分を学び直す意義もあると考える人もいます。
教育勅語の一部(原文と現代語訳)
「父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和シ、朋友相信シ…」
(現代語訳:親に孝行し、兄弟仲良くし、夫婦は仲むつまじく、友人とは信頼し合う)
このように、教育勅語は個人の道徳と国家への忠誠を結びつけた文書であり、明治時代の日本人の「理想の姿」を示していたといえます。
まとめ
- 教育勅語は明治天皇が発した教育の基本方針を示す文書
- 家庭や社会での道徳と国家への忠誠を説いている
- 戦後は廃止されたが、道徳的価値は現代にも通じる部分がある
教育勅語は、単なる歴史上の文書ではなく、「日本人がどのような心で生きていくべきか」を考える手がかりにもなります。
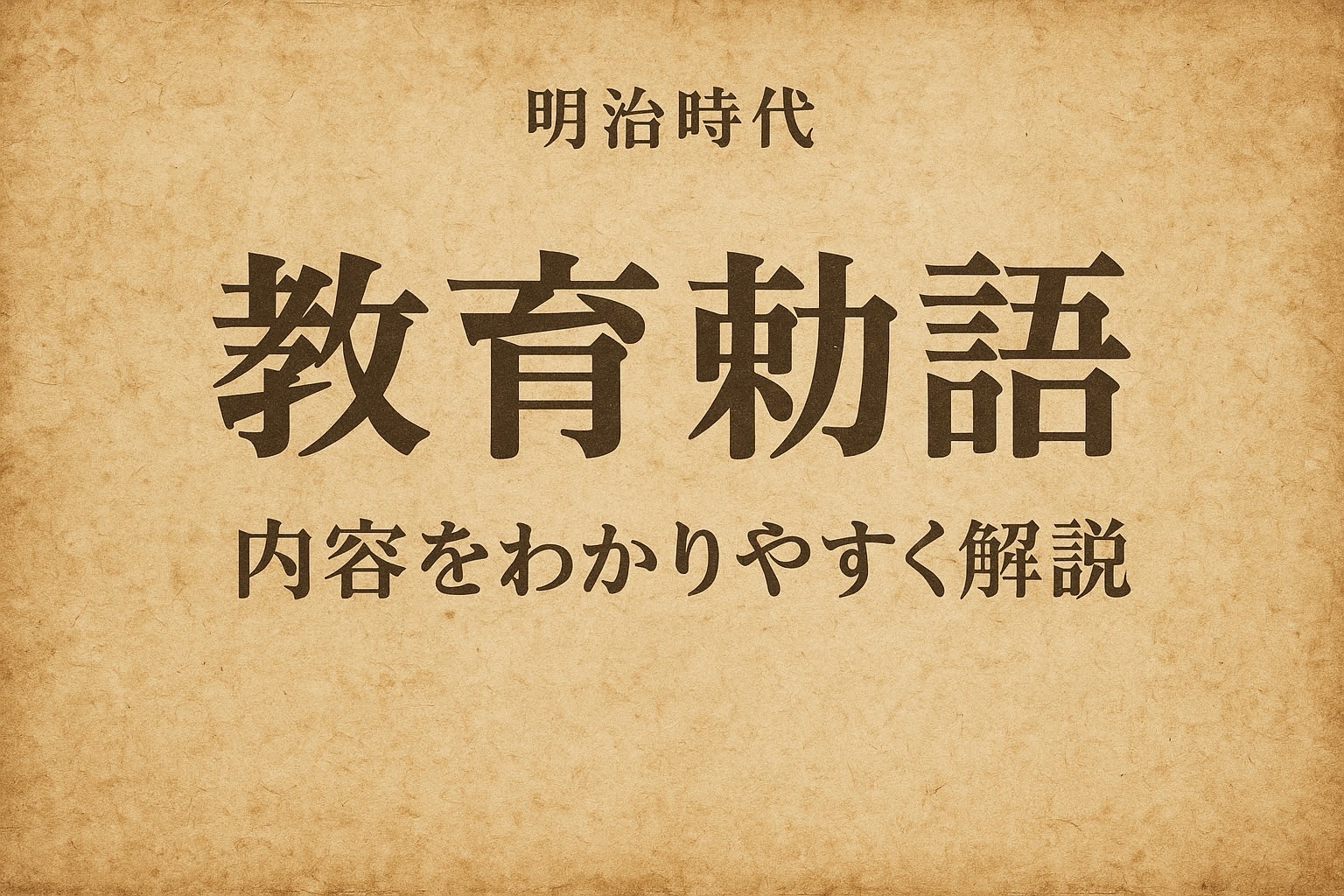


コメント